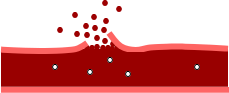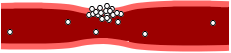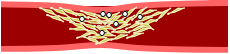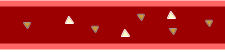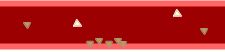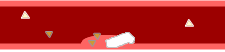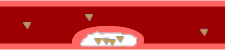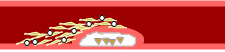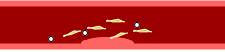いったいどんな病気なのか、みてみましょう
|
||||||||||||||||||
|
血栓とは、血管の中にできる 血の塊のことです。 血栓ができる仕組みは、まず、血管が破れて出血が起こると、そこに血液中成分のひとつである血小板が集まって互いに集まって互いにくっつき合って固まります(とりあえずの止血、血小板血栓という)。 (図1−②を参照) しかし、これだけでは止血は不十分として、次に、正常では血液に溶けているフィブリノーゲンというタンパク質が「フィブリン」(線維素ともよぶ)という固形に変化して、さらにしっかりと血管の破れた場所を止血します(血液凝固)。 (図1−③を参照) そしてそれを土台にして、破れた血管壁の細胞が増殖し、血管は修復されます。 (図1−④を参照) このフィブリンがいわゆる血栓の正体です。 さて、このままフィブリンの塊(血栓)が残っていては、血管がふさがれた状態が続くため、血液が流れることができません。 しかし、私たちの体には用済みとなったフィブリン(血栓)を溶かすしくみが備わっています。 これが「線溶系」というシステムです。 この線溶系が活性化すると、フィブリンの塊が溶かされ、 (図1−⑤を参照) 血液が再びスムーズに流れるわけです。 (図1−⑥を参照) この線溶系の働き、すなわち血栓を溶かすしくみですが、血栓ができると血液中にあるプラスノーゲンという物質が活性化されて、プラスミンという酵素に変換されます。 このプラスミンが血栓の正体であるフィブリンを溶解します。 このように、通常、血液は、固まろうとする凝固系の働きと、血栓を溶かそうとする線溶系の働きと、がバランスを取り合っています。 健康な人ほど、この生体の防御機能がバランスよく備わっているといえるでしょう。 このバランスが乱れて、線溶系の働きが低下すると血栓が生じやすくなり、一方、線溶系が活発になると出血を起こしやすくなります。 高齢になると、この線溶酵素の働きが衰えてくるので、できた血栓を溶かすことができず、血栓症が起こりやすくなると考えられています。 また、問題なのは、血管が破れた時に血小板が働いて血液を凝固させ出血を止めてくれるしくみが、何らかの事情で血管の内皮細胞が損傷したときにも、全く同様の過程が進んでしまい、血栓症が引き起こされるということです。 これは動脈硬化というものです。 食生活の欧米化が進んだり、食べ過ぎていると、まず、血液中の中性脂肪やコレステロールの値が高くなります。 そのコレステロールが血液の中で酸化されると、血管の内皮細胞の細胞膜を酸化傷害することがあり、そこから、血管の中にもぐりこんだマクロファージ(大食細胞)が酸化コレステロールを食べ続け、血管壁にコブができて、そこに、血小板やフィブリンが溜まりはじめます。そして血栓ができてしまうという結果になります。 (図2−①②③④を参照) このように、血管が破れたわけでもないのに、血管の内皮細胞が酸化傷害などによって傷ついたりすると、血小板を含む凝固系は、止血の時と全く同様に働いてしまい、血栓ができてしまうのです。 (図2−⑤を参照) 動脈硬化は、50歳を過ぎると3人に1人といわれ、老化現象の一つとみなされてきましたが、、ここ数十年に若い世代にもにも広く広がっていると警鐘が鳴らされています。 もし、血栓が血管をふさいでしまうと、どうなってしまうのでしょうか。 そこから先には血液がいかなくなり、細胞への酸素や栄養分の供給がストップしてしまいます。その結果、細胞組織は壊死してしまいます。 これが、心臓の血管に起これば心筋梗塞、脳の 血管に起これば脳梗塞となります。 日本人の死因は、第一位がガン、第二位が心筋梗塞、第三位が脳卒中であることはよく知られています。 しかし、第二位の心筋梗塞と第三位の脳卒中は、どちらも血栓が引き金となる「血栓症」による共通の病気ですから、そうであれば、 日本人の死因のトップは血栓症! ということになります。 <もどる> |
|||||||||||||||||